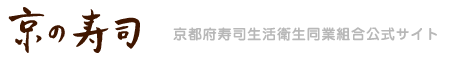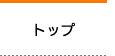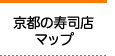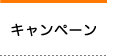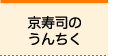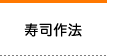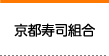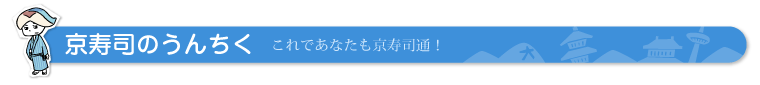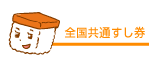にぎり寿司より長い歴史を持つ、「京寿司」をご存知ですか?新鮮な魚が手に入らない京都で、独自の発展を遂げてきた京寿司は、京都を代表する食文化の1つ。見た目の美しさと、上品な味付けからは、かつて朝廷に献上されていた京寿司の歴史を感じることができます。今なお、祇園祭や葵祭など、京都のお祭りには欠かせないこのお寿司。ここでは、人々に愛され続ける京寿司の一端をご紹介いたします。
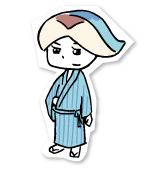
鯖寿司
その昔、鮮魚の手に入りにくかった京都の人々にとって、日本海で取れた塩漬けの鯖は大変なご馳走でした。その鯖を酢で締め、すし飯と合わせたのが鯖寿司のはじまり。鯖寿司は今でも、お祭りやお祝いの席で出される特別なお寿司です。2、3日経っても食べられる優秀な保存食の鯖寿司。1日置いた頃が、鯖とシャリがなじみ、最もおいしくいただけます。
![]()
鯖之介
お寿司屋「京寿司」の跡継ぎを志す、大学4回生。サバサバした性格と、顔、スタイルの良さから、大変よくモテるが、現在は寿司修行一筋という硬派な男の子。

にぎり寿司
おすしの歴史は約2000年。奈良時代に書かれた「日本書紀」の中に残っている、鶚(みさご)ずしの記述が最も古いものと言われています。もともとご飯は発酵のために使われ、乳酸発酵した魚のみを保存食として食べていました。今でも鮒寿司はそうですね!当時の名残で、京都ではお寿司をつくることを「つける」と言います。にぎり寿司は1824年に江戸で生まれました。
![]()
にぎり姫
なんでも白黒つけたがる、はっきりタイプの女子大生。面倒見がよく、お母さん的存在。

ちらし寿司
ばら寿司とも呼ばれるちらし寿司。見た目も鮮やかで、お祝いごとに欠かせない一品ですが、京都のちらし寿司には生ものは乗せません。時間が経っても大丈夫なように、火を通したものや、お酢で締めたものが盛られています。じゃこや、錦糸卵など家庭で手に入る具材でつくられたちらし寿司をお台所寿司とも言います。
![]()
ばら小町
ちょっと内気で引っ込み思案なところがある優しい女子中学生。細かい作業が得意。

巻き寿司
関西寿司の代表格—巻き寿司。1776年に書かれた料理書「献立部類集」に記載されている歴史あるお寿司の1つです。その巻き寿司、京都は丸、大阪は四角、関東はかまぼこ型と地域によってそれぞれ形が違います。また、かんぴょうの色が薄いのが京都の巻き寿司の特徴。黄色い卵に、緑の三つ葉、うす茶色のかんぴょうと彩りにこだわって作られたのが京都の巻き寿司です。
![]()
巻若丸(通称:マッキー)
まだまだやんちゃな小学5年生。周りを楽しませるのが大好き。パーティにはかかせない存在。
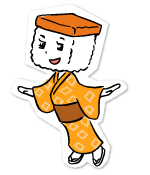
箱寿司
肉厚で脂の乗ったはもを骨切りにし、薄味で蒸し煮にしたものをさらに細かくたたき、押し寿司にしたものが京都の箱寿司。はもだけでなく、サワラもよく使われます。主にアナゴを使う大阪の箱寿司との違いですね。タマゴ、エビ、白身魚が盛られたケラ箱と呼ばれる箱寿司もあります。
![]()
おはこ
天真爛漫でちょっとドジな小学5年生の女の子。狭いところが大好き。にぎり姉さんに憧れている。